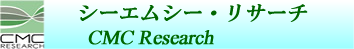S&T出版ウェビナーのご案内
開催日時:2024年8月5日(月)13:00~15:00
受 講 料:35,200円(税込) ※ 資料付
会 場:【WEB限定セミナー】※在宅、会社にいながらセミナーを受けられます。
備 考
<Webセミナーのご説明>
本セミナーはZoomウェビナーを使用したWebセミナーです。
※ ZoomをインストールすることなくWebブラウザ(Google Chrome推奨)での参加も可能です。
お申込からセミナー参加までの流れは こちらをご確認下さい。
<禁止事項>
セミナー当日にZoomで共有・公開される資料、講演内容の静止画、動画、音声のコピー・複製・記録媒体への保存を禁止いたします。
配付資料について
本セミナーの資料はPDF形式(電子データ)で配布予定です。
開催日前日までにダウンロードURLお送りいたします。
※セキュリティポリシー等でダウンロードできない方はご連絡ください。
その場合はe-mail添付にてお送りいたします。
※両方法共に受け取れない方は、開催後にプリントしてお送りいたします。
お申し込み受付中
申込方法
下記のカートへの投入、あるいはFAX用紙にてお申込ください。
| FAX申込用紙PDF |
講 師
金子 健太郎 氏
立命館大学 総合科学技術研究機構 教授 RARAフェロー
<講師略歴>
2008年 大阪府立大学(現大阪公立大学)工学部機能物質科学科 卒業
京都大学大学院工学研究科電子工学専攻博士前期課程 入学
2010年 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻博士後期課程 進学
日本学術振興会特別研究員(DC1) (京都大学工学研究科 電子工学専攻)
2013年 京都大学大学院 工学研究科 電子工学専攻 博士課程 修 博士(工学)
日本学術振興会特別研究員(PD) (京都大学工学研究科 材料化学専攻)
2014年 京都大学 工学研究科 附属光電子理工学教育研究センター 助教
2018年 京都大学 工学研究科 附属工学基盤教育研究センター 講師
2021年 京都大学 工学研究科 附属光電子理工学教育研究センター 先進電子材料分野 主宰
2022年 立命館大学 総合科学技術研究機構 教授
2023年 立命館大学 先進研究アカデミー(RARA) フェロー 選出
2024年 立命館大学 半導体応用研究センター(RISA) センター長
【これまでの研究内容】
2008年
4回生の卒業研究では、PLD法によりZnMgO/ZnO積層構造を作製し、2次元電子ガス層形成による凝縮系電子状態の研究を行った。
2009-2013年
博士課程大学院在籍時には酸化ガリウム黎明期の初期研究を行った。藤田静雄教授(現京都大学名誉教授)御指導のもと、当時藤田研で薄膜作製に成功していたコランダム構造酸化ガリウム(α-Ga2O3)に注目し、酸化鉄(α-Fe2O3)との混晶化による混晶磁性半導体の作製と磁気的評価、酸化アルミニウム(α-Al2O3)や酸化インジウム(α-In2O3)との混晶化によるα-Ga2O3のバンドギャップ変調など、コランダム構造酸化物を用いた電気デバイス応用、特にパワー半導体応用の基礎となる研究を行った。
2014-2020年
藤田研究室の助教、講師として、酸化インジウム(α-In2O3)を用いたMOSFET作製と動作実証、酸化ガリウム(α-Ga2O3)のp型作製が理論的・実験的に不可能である事の実験的証明、そしてp型が作製できない酸化ガリウムのためのp型層開拓などを行った。特に酸化ガリウム(α-Ga2O3)のp型層として、同じコランダム構造をもつ酸化イリジウム(α-Ir2O3)および酸化イリジウムガリウム(α-(Ir,Ga)2O3)を開発し、ヘテロ接合構造による整流性の実証も行った。
2021-現在
京都大学の研究室PIとして先進電子材料分野を主宰し、p型が作製出来ない酸化ガリウムの弱点を克服するために、p型とn型の作製が理論的に予測されていたルチル構造二酸化ゲルマニウム(r-GeO2)に着目し、改良型ミストCVD法を用いて作製に成功した。
立命館大学異動後は、このルチル構造二酸化ゲルマニウム(r-GeO2)の初期開拓をはじめ、水銀灯の真空紫外領域波長(185nm)で発光可能な酸化マグネシウム亜鉛(MgZnO)や、燃料電池の低コスト化の要となるステンレスセパレータ用の耐腐食導電性コート材料の開発、半導体作製プロセスに用いる絶縁性の開発など、パワー半導体材料研究のみならず、新しい酸化物材料の開拓や既存材料の新規応用先開拓を行っている。
【学会活動】
2018年-現在
IEEE CPMT Symposium Japan (ICSJ) 運営委員、査読委員パワーデバイスセッション責任者
2021年-現在 エレクトロニクス実装学会関西支部 役員
2019年-現在 日本結晶成長学会 ナノ構造・エピタキシャル成長分科会 幹事
2018年-現在 日本材料学会 第67期 編集委員会 査読委員
2022年-2023年 応用物理学会 代議員
2021年-2022年 日本材料学会 半導体エレクトロニクス部門 編集担当委員
2020年-2023年
第4回酸化ガリウムおよび関連材料に関する国際ワークショップ(IWGO-4) 財務
2019年-2021年 電子材料シンポジウム(EMS) 現地実行委員
2019年-2021年 応用物理学会 関西支部 幹事
2019年-2021年 日本材料学会 半導体エレクトロニクス部門 編集副担当委員
2016年-2019年 有機金属気相成長法国際学会 ICMOVPE -XIX 現地実行委員
2014年-2015年
第1回酸化ガリウムおよび関連材料に関する国際ワークショップ(IWGO2015) 財務
2014年 テラヘルツプラズマ国際学会2014 現地実行委員、会計
【主な受賞歴】下記賞を含む25件の賞を受賞
(1) 第23回船井学術賞 2024年5月18日
(2) 応用物理学会関西支部 第15回関西支部貢献賞 2023年3月13日
(3) 日本結晶成長学会 奨励賞 第20回奨励賞 2022年11月1日
(4) IEEE CPMT Symposium Japan 2018 Best Paper Award 2018年11月19日
(5) 日本材料学会 学術奨励賞 2018年5月26日
(6) 平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞 2018年4月17日
(7) 第30回 安藤博記念学術奨励賞 2017年6月24日
(8) 第38回 本多記念研究奨励賞 2017年5月29日
(9) 第4回 京都SMI中辻賞 2017年2月21日
(10) 第5回 エヌエフ基金 研究開発奨励賞 優秀賞 2016年11月25日
(11) 第14回 船井研究奨励賞 2015年4月18日
(12) 第31回 井上研究奨励賞 2015年2月4日
(13) 第31回(2011年秋季)応用物理学会講演奨励賞
セミナーの趣旨
昨今、パワー半導体業界には新材料による新たな市場形成が始まっています。例えばSiCはこの10年間の大幅な低価格化により徐々に市場に浸透し始めており、高周波デバイス用途ではGaNが絶対的な地位を築こうとしています。そして近い将来、SiCやGaNより大きなバンドギャップをもつより高性能なデバイスが必要になります。しかし、新材料が市場で受け入れられるには厳しい条件をクリアしなければいけません。それは①基板、薄膜、加工のコストが低い、②SiCやGaNよりも優れた低損失性、③p型とn型のドーピング手法による作製の実現性、の3つが基本条件です。本セミナーではその条件をクリアし、候補材料となり得る新しいパワー半導体材料であるルチル構造二酸化ゲルマニウム(r-GeO2)の物性や作製手法についてお話をします。
プログラム
1. SiC、GaNの今後の動向
2. 新しいパワーデバイス材料、二酸化ゲルマニウム(r-GeO2)の可能性
2-1 r-GeO2の可能性
・バンドギャップ4.6 eV
・p型とn型が作製可能(理論予測)
・高い移動度、安価に基板作製可能
2-2 なぜ、r-GeO2の薄膜合成は困難なのか?
2-3 r-GeO2厚膜の合成
2-4 r-GeO2混晶
2-5 世界のr-GeO2研究